
目次
- 1 【七五三とは?】奈良のフォトスタジオが必要知識を網羅的に解説
- 1.1 七五三とは?意味や由来について
- 1.2 七五三の3歳、5歳、7歳で着る子供着物について
- 1.3 七五三の参拝・祈祷について
- 1.3.1 七五三の際の参拝・祈祷とは
- 1.3.2 七五三のお参りのいつが混雑するかおすすめの時期は?
- 1.3.3 七五三のお参りは六曜(大安・先勝・先負・友引・赤口・仏滅)を気にするべきか
- 1.3.4 七五三のお参りは神社やお寺などどこへ行くべきか
- 1.3.5 七五三お参りの際の作法・作法・マナー
- 1.3.6 七五三初穂料とのし袋(熨斗袋)の事前準備と初穂料の料金相場
- 1.3.7 七五三の祈祷後にもらえることの多い千歳飴とは
- 1.3.8 七五三参拝・祈祷の際の持ち物
- 1.4 奈良で七五三の写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ
【七五三とは?】奈良のフォトスタジオが必要知識を網羅的に解説
子供が3歳、5歳、7歳を迎えた際にお祝いする七五三。
初めて七五三を迎える家庭は沢山の疑問と不安があるかと思います。
この記事では七五三に関する必要な知識を網羅的に解説し、この記事を読み終わった後に七五三に関する不安や不明点が残らないようにします。
七五三とは?意味や由来について
七五三とは?七五三の意味
七五三は日本の伝統行事で、お子様が3歳、5歳、7歳という重要な節目の年に、子供の成長を神様に感謝し、今後の健やかな成長をお祈りする行事です。
神社やお寺に参拝し、祈祷を受けたり、写真館で記念の写真を撮ることが一般的です。
七五三の由来:なぜ3歳、5歳、7歳で七五三のお祝いをするのか
七五三は平安時代や鎌倉時代に行われていた子供の成長に感謝する3つの儀式が元になっています。
それぞれ3歳、5歳、7歳の節目に子供の成長に対して神様に感謝し、お祝いをしました。
当時は現代に比べ医療も発達していなかったため、乳幼児の死亡率が高く、7歳まで生きられる子供も多くなかったため、このような儀式があったと言われています。
なぜ七五三は3歳、5歳、7歳になったのかは、2つの説が有力です。まず1つ目は、奇数が縁起良いとされていたという説です。上記3つの儀式が中国から伝わった際に、奇数が縁起良いとされていたことから3歳、5歳、7歳に儀式が行われるようになったという説です。もうひとつは、3歳、5歳、7歳が成長の中での、節目のタイミングだからという説です。3歳が言葉を理解する時期、5歳が知恵のつく時期、7歳が乳歯の生え変わる時期として、成長の中の節目の歳を選んだという説です。これら2つの説から七五三が3歳、5歳、7歳の時期に行われるようにと言われています。
七五三の由来となった儀式
髪置の儀:3歳の七五三の由来となった儀式
髪置の儀は3歳で子供が髪を伸ばし始めるタイミングをお祝いする儀式でした。
平安時代の頃は、衛生面から頭を清潔に保ち病気の予防をすることを目的に、男女とも3歳まで丸坊主で育てるという風習がありました。
3歳の春を迎える頃に、髪置きの儀では、長寿を祈願するために白髪を模した白糸や綿白髪を頭上において祝ったとされています。
白髪を模したのは、白髪が生えるまで、長生きしますようにという願いが込められたと言われています。
袴着の儀:5歳の七五三の由来となった儀式
袴着の儀は5歳の男の子が初めて袴をつけることをお祝いする儀式でした。
昔は5歳から男女異なる衣服を付けるようになっていました。
袴着の儀は当初、男女ともに行っていた儀式でしたが、江戸時代から男の子のみの儀式に変わったと言われています。
儀式では基盤の上で吉方を向いて、縁起が良いとされる左足から袴を履き、お祝いをしました。
帯解の儀:7歳の七五三の由来となった儀式
帯解の儀は7歳で帯を使って着物を着るようになることをお祝いする儀式でした。
帯解の儀以前は、着脱がしやすいように紐がついていた着物を着ていました。
7歳になるとその紐をとり、腰ひもと帯を結んで着物を着るようになりました。
帯時の儀は当初は9歳でしたが、近世に近づくにしたがって、7歳で行うようになっていったと言われています。
七五三は数え年と満年齢のどちらでやるべきか?
まず、満年齢と数え年とはそもそも何かについて解説します。
満年齢とは現代の一般的な年齢を指し、生まれた時を0歳として、1歳のお誕生日が来ると1歳とする考え方です。
一方数え年は生まれた日を1歳と数え、元日が来ると1歳足す考え方で、昔の年齢の数え方になります。
七五三を満年齢と数え年のどちらでするは、結論どちらでも問題はありません。
ただし、数え年で七五三をする場合と、満年齢で七五三をする場合にはいくつか注意点があります。
数え年で七五三をする場合の注意点は、3歳の数え年で七五三をする場合にあります。
3歳の数え年のお子様は満年齢の2歳になり、イヤイヤ期の最中のお子様や、まだママから離れられないお子様もいます。
この場合、写真撮影や神社へのお参りの際、お子様が着物を嫌がる可能性があります。
せっかく家族や祖父母とも予定を合わせたのに、お子様が着物を嫌がり、その結果、着物で七五三ができなかったとなる可能性があります。
3歳の数え年で七五三を考えている場合は、子供の様子をみながら判断しましょう。
上記のような理由から、七五三の実施は難しそうだが、どうしても数え年3歳(満年齢2歳)のあどけない姿を写真で残しておきたい場合は、写真館で2歳バースデーの写真撮影を利用するのがおすすめです。
また、満年齢で七五三をする際の注意点としては、体調不良や不幸事など何かしらの理由で七五三を急遽、実施できなくなり、翌年にする場合、1歳すぎた状態で七五三を迎えることになります。
数え年で、何かしらの理由で七五三を実施できなかった場合、翌年満年齢にて七五三の実施ができます。
しかし、満年齢の場合に何かしらの理由で七五三を実施できず、翌年に七五三の実施をする場合、3歳・5歳・7歳を1歳過ぎた状態で七五三をすることになります。1歳過ぎても七五三の実施はできますが、体に合う着物の種類が少なくなったりする可能性があります。
また、満年齢5歳の七五三でお宮参りの際の産着をもう一度使用したいと考えている方も注意が必要です。
お宮参りの際の産着は、満年齢の5歳だとサイズが小さくなっている可能性が高いです。
そのため、お宮参りの産着を5歳の七五三で使用したいと考えている方は、数え年の5歳(満年齢4歳)に七五三の実施を検討するのがおすすめです。
数え年の5歳でも体格が大きいお子様の場合は、サイズが合わない可能性もありますので、一度産着を購入した呉服店でサイズを測ってもらうと良いでしょう。
七五三の日は何月何日?
七五三の日は11月15日とされています。
七五三の日が11月15日とされる理由には、いくつかの説があります。
代表的な説は、まず11月になったのは、収穫を終え神様に感謝する時期が11月という説があります。
また、15日になった説は、
・15日が鬼の出歩かない日とされ吉日とされた説
・七五三の7と5と3を足すと15になるという説
・徳川綱吉の子の徳松の健康祈願のお祝いが11月15日だったという説
などがあります。
七五三の3歳、5歳、7歳で着る子供着物について
七五三の子供着物のパターンは、
・被布スタイル
・羽織袴スタイル
・着物&帯(作り帯) スタイル
・着物&帯(手結び帯) スタイル
・お宮参りの産着を仕立て直しスタイル
などがあります。
3歳の女の子では被布スタイルが最も多く、次に着物&帯の作り帯のスタイルが続きます。
3歳の男の子では羽織袴スタイルが最も多く、次に被布スタイルが多くなっています。
5歳の男の子では羽織袴スタイルが大半になっています。
7歳の女の子では着物&帯の作り帯のスタイルが大半になっています。
また、される方は多くはないですが、3歳と5歳の七五三ではお宮参りで使用した産着を仕立て直して、もう一度使われる方もいます。ここではそれぞれのスタイルの特徴と必要なものについて解説していきます。
被布スタイル:3歳の女の子の七五三着物で最も多いスタイル
・被布スタイルの対象
被布スタイルは3歳の女の子の七五三にて最も多いスタイルです。
3歳の男の子の七五三では羽織袴スタイルに次いで、2番目に多いパターンになります。
・被布スタイルの特徴
被布スタイルの特徴は、帯を締めなくてもきれいに着こなせることがあります。
締め付けが少ないため、お子様への負担が少なくなります。
また着付けが簡単という特徴もあります。
・被布スタイルに必要なもの
被布
被布は着物の上から着用する羽織物になります。
ベストのような形で、袖はなく、衿はある形をしています。
首元は四角く空いたデザインになっています。
着物
被布スタイルは3歳の七五三で利用することが一般的なため、三つ身の子供用の着物を使用します。
子供の成長を考慮し大き目に作られていることも多いため、必要に応じて肩上げや腰上げのサイズ合わせを行います。
長襦袢
長襦袢は着物の下に着て、着物に直接肌が触れるのを防ぎます。
衿部分に半衿をつけ、着物の衿元が汚れるのを防ぎつつ、華やかに見せます。
こちらも必要に応じて肩上げというサイズ調整を行います。
肌襦袢or肌着
肌襦袢は和装における肌着にあたるもので、長襦袢の下かつ素肌の上に着用します。
肌襦袢は長襦袢に汗や皮脂などの汚れが直接付くのを防ぐ役割があります。
また、肌襦袢は肌着(首物の高くないU字やV字のシャツ)でも代用できます。
シャツで代用する場合は、脇汗をかいて着物を汚してしまう可能性があるので、ノースリーブのシャツは避けます。
腰紐
腰紐は長襦袢や着物を着付ける際に使用する紐で、着丈を調整し、着崩れを防ぐ役割があります。
年齢によっても異なりますが、大体3~5本くらいあると良いでしょう。
足袋
足袋は和装の靴下にあたります。子供の七五三の場合は伸縮性のあるものが便利です。
草履
草履は和装の際の基本的な履物になります。
男の子の場合は白い鼻緒のものを使用し、女の子の場合は着物に合わせた鼻緒のものを選ぶと良いでしょう。
髪飾り
ヘアセットをされる場合は髪飾りもあると良いです。
羽織袴:3歳男の子、5歳男の子で最も人気のスタイル
・羽織袴スタイルの対象
羽織袴スタイルは3歳・5歳の男の子の七五三で最も多いスタイルとなっています。
・羽織袴スタイルの特徴
羽織袴スタイルは着物に角帯を締め、袴をつけ、その上から羽織を着ます。
また、短刀を袴に差し末広(扇子)を手に持ちます。
着付けは比較的簡単なため、15分~30分ほどで着付けができます。
・羽織袴スタイルに必要なもの
着物
羽織袴スタイルは3歳・5歳の男の子の七五三で利用することが一般的なため、三つ身の子供用の着物を使用します。
子供の成長を考慮し大き目に作られていることも多いため、必要に応じて肩上げや腰上げのサイズ合わせを行います。
羽織
羽織は着物の上に重ねて着る男性和服の礼装です。
必要に応じて肩上げをしてサイズの調整を行います。
羽織紐
羽織紐は羽織の前がはだけないように留めるための紐です。
房が付いているものが一般的です。
子供の七五三用の場合、紐先端に金属のフックがついているので、羽織の左右にかけて取り外しします。
長襦袢
長襦袢は着物の下、肌襦袢の上に着ます。
汗や垢などで着物が汚れるのを防ぐ役割があります。
衿部分には半衿をつけ、着物の衿元が汚れるのを防ぎ、華やかに見せます。
肌襦袢・肌着
肌襦袢は和装の下着にあたるもので長襦袢の下、素肌の上に着ます。
長襦袢や着物に汗や汚れが付くのを防ぐ役割があります。
肌襦袢は深めのU字やV字のシャツでも代用ができます。脇汗で着物が汚れるのを防ぐため、ノースリーブやタンクトップは避けます。
袴
袴は洋装でいうズボンにあたり男性和装の礼服になります。
角帯
角帯は着物の上から締める帯になります。
長襦袢や着物を固定するために使用します。
腰紐
腰紐は長襦袢や着物を着付ける際に使用する細めの紐になります。
使用する本数は体型などによって異なりますが、3本ほどあれば良いです。
足袋
足袋は和装の靴下にあたります。
一般的には白足袋を用います。
子供の七五三の場合は伸縮性のあるものが便利です。
草履
草履は和装の際の基本的な履物になります。
一般的には男の子の場合は白い鼻緒のものを使用します。
懐剣
懐剣は帯と袴の間に刺す短剣になります。
現在は本当の刀ではなく、装飾品を用います。
魔除けや招福という意味合いがあります。
扇子(末広)
扇子は未来が広がり幸せになるという願いが込められた縁起物になります。
袴を着付けた際の帯に差すか、手に持って使います。
お守り
お守りは、元々は魔除けの目的で身に付けられていました。
現在は装飾品としての意味合いが強くなっています。
着物&帯スタイル:7歳女の子で最も人気のスタイル
・着物&帯スタイルの対象
着物&帯スタイルは、3歳の女の子で、被布に次いで人気のパターンになります。
また7歳の女の子では最も人気のパターンとなっています。
・着物&帯スタイルの特徴
着物&帯スタイルの特徴としては、着物の柄が良く見えるという特徴があります。
その他は被布よりも着付けに時間がかかることや、帯でお腹周りを締めるので、2~3歳の子供には負担が大きい可能性があります。
・着物&帯スタイルの種類【作り帯と手結び帯】
着物&帯スタイルの種類としては、作り帯のパターンと手結び帯のパターンがあります。
作り帯は、着物に巻き付ける部分と飾りの部分の2つに分かれています。
帯の形が既に出来上がっており、手結び帯よりも着付がしやすくなっています。
ただし、個性的な結び方はしにくいという特徴があります。
また、手結び帯のパターンは帯が長いひも状の一本になっています。
帯の結び方によって個性的な結びをすることができます。
ただし、着付け師への依頼に時間と費用がかかります。
・着物&帯スタイルに必要なもの
着物
着物は7歳の女の子には、四つ身の着物を使用します。
子供用の着物は成長を加味して大きめに作ってあることも多いので必要に応じて肩上げや腰上げのサイズ調整を行います。
肩上げには子供の成長を願うという意味が含まれています。
重ね衿(伊達衿)
重ね衿(伊達衿)は、元々着物を2枚重ねにして着ていたことの名残で用います。
着物の衿元に縫い付け着物の衿元を華やかに見せます。
長襦袢
長襦袢は着物の下に着て、着物に汗や皮脂の汚れが付くのを防ぎます。
襟元に半衿を縫い付けます。
肌襦袢・肌着
肌襦袢は長襦袢の下、素肌の上に着用し、長襦袢や着物に汗や汚れが付くのを防ぎます。
普段着用している深めのU字やV字のシャツで代用できます。
帯
7歳の七五三では大人と同じように帯を締めます。
帯には前述の既に帯の形が出来上がっている作り帯と、ひも状の一本の状態から結ぶ手結び帯とがあります。
帯揚げ
帯揚げは帯の形をきれいに整える帯枕と、帯枕についている紐を隠すために用いる布です。
着物を帯の上側の境目部分を隠すように巻き付けます。
また着物を華やかに見せる役割もあり、帯が作り帯のパターンでは装飾品としての役割が強くなります。
帯締め
帯締めは帯が緩んだり崩れないように帯の上から締める紐になります。
一般的には中に綿の入った丸ぐけと呼ばれる帯締めを使用します。
また、着物を華やかにする装飾品としての役割も兼ねています。
しごき
しごきは一枚の布をしごいて縮めた布で、薄く柔らかい生地で作られています。
帯の下の斜め後ろで蝶々結びにします。
もとは女性が長い裾を上げるために使用していたものですが、現在は七五三の着物を華やかにする装飾品としての役割が強くなっています。
腰紐
腰紐は着物や長襦袢を着付けるために結ぶ細めの紐です。
7歳の七五三の場合は大体3~5本くらいを目安に準備をします。
タオル
華奢な女の子の場合、お腹の周りにボリュームを出し、補正をするためにタオルを使うことがあります。
伊達締め
衿が浮くのを防いだり、おはしょりの着崩れを防ぐために使うことがあります。
筥迫
筥迫は紙入れの一種で箱の狭いものという意味から来ています。
開かないように、胴締めというもので止められています。
胴締めには占めるための紐と巾着がついています。
従来は巾着の中にはお香やお守りを入れ、本来隠れているものでしたが、徐々に装飾品としての役割が強くなってきました。
びら簪
びら簪は筥迫に差し込んで使う金属の飾りになります。
扇子(末広)
おめでたい柄が書かれた房飾りがついた小さめのサイズのものを使用します。
扇子(末広)にはお子様の人生が末広がりに栄えますようにという願いが込められています。
帯と帯締めの間に刺し、装飾品としても使います。
髪飾り
髪飾りは髪につけてヘアスタイルを華やかにするための小物です。
足袋
足袋は和装の靴下にあたります。
一般的には白足袋を用います。
子供の七五三の場合は伸縮性のあるものが便利です。
草履
草履は和装の際の基本的な履物になります。
男の子の場合は白い鼻緒のものを使用し、女の子の場合は着物に合わせた鼻緒のものを選ぶと良いでしょう。
帯枕
帯枕は帯を立体的に整えるための道具です。
7歳の七五三では手結び帯のパターンの際に主に使用します。
帯を結ぶ際にお太鼓の土台にし、帯結びを安定させます。
帯板
帯板は帯の形を整えるための道具です。
7歳の七五三では手結び帯のパターンの際に主に使用します。
帯板を使うと帯の前部分がピンと張った状態に見せることができるため、シワのない美しい仕上がりになります。
三重仮紐
三重仮紐は華やかな帯結びの際に必要となる紐です。
手結び帯のパターンの際に主に使用します。
お宮参り産着スタイル:お宮参りで購入した着物を七五三で使用
・産着の仕立て直しスタイルの対象
3歳もしくは5歳の七五三では、お宮参りの産着を仕立て直して利用することができます。
5歳の七五三の場合、サイズの問題から、数え年の5歳の時期だと使用できる可能性があります。
・産着の仕立て直しスタイルの特徴
七五三用の仕立て直しは一度しても、下の子供用に再度お宮参りの産着に仕立て直しをすることができます。
注意点としては、仕立て直しに費用と時間がかかることや、産着の仕立て直しをしても七五三のお参りの際は、被布や袴などその他の部分は必要に応じてそろえる必要があります。
産着を七五三用に仕立て直す際は、袖口を作ること、腰上げ、肩上げ、紐を取るもしくは位置を変えることが必要になっています。
産着を七五三用に仕立て直す場合はどこに持って行けば良いか
産着を七五三用に仕立て直す場合は、産着を購入した呉服店にて仕立て直しをしてもらうのがおすすめです。
引っ越しなどで、産着を購入した呉服店に行くことが難しい場合は、近所の呉服店に相談しましょう。
産着を七五三用に仕立て直す際の費用と時間は
産着を七五三用に仕立て直す際の費用は大体5,000円~20,000円くらいが相場となっています。
産着を買った呉服店かどうかで料金が変わることがあります。
仕立て直しの期間としては、1か月~2か月くらいが一般的なため、計画的に進めていきましょう。
産着を七五三用に仕立て直しをした際に、産着の他に必要となるもの
産着を七五三用に仕立て直しをした際に、産着の他に必要になるものは、被布のパターンにするのか羽織袴のパターンにするのかによって異なります。
被布のスタイルにする場合は、被布や長襦袢、肌襦袢、腰紐、足袋、草履などが必要になってきます。
さらに女の子の場合は巾着や髪飾りも必要に応じて準備します。
また、羽織袴のスタイルにする場合は、羽織や羽織紐、長襦袢、肌襦袢、袴、角帯、腰紐、足袋、草履、懐剣、扇子などが必要になってきます。
こちらは当日着付けをしてもらうお店があれば、そちらに問い合わせをしてみましょう。
七五三着物の身上げ(肩上げ・腰上げ)
七五三用の着物は成長に合わせて、仕立て直せることを前提に少し大きめの作りになっています。
肩上げ、腰上げは大きめに作られている着物を子供の身体に合わせて縫い上げる作業です。
肩上げ・腰上げをまとめて身上げとも呼びます。
肩上げは裄丈(首の根本~手首までの長さ)を調節する作業です。
腰上げは身丈(首の根本~足首までの長さ)を調整する作業です。
また、肩上げにはお子様のこれからの成長を願うという意味も込められています。
七五三の参拝・祈祷について
七五三の際の参拝・祈祷とは
七五三のお参り・参拝とは神社やお寺を訪れ、神様や仏様を拝むことを指します。
七五三のお参り・参拝は、
・お賽銭を入れ拝礼のみするパターン
・お賽銭を入れ拝礼&ご祈祷を受けるパターン
があります。
お賽銭を入れ拝礼する場合は、神社に訪れ、お賽銭箱にお賽銭を投入し、神様に感謝をしたり、加護をお願いしたりします。
祈祷とは社殿にあがって神職に祝詞をよんでもらい、神様にお願いを伝える儀式です。
ご祈祷はお賽銭を入れて拝礼することに比べ、より丁寧なお参りの方法と言えます。
また、祈祷と似た言葉に祈願がありますが、祈祷は神職に行ってもらうものに対し、祈願は自身が神様に願いを捧げることを指す場合が多いです。
七五三のお参りを考えている方は、お賽銭を入れて拝礼のみをするか、お賽銭を入れて拝礼&祈祷を受けるかをします。
祈祷は予約が必要な神社と予約が不要な神社があります。
神社での祈祷は大体9時~16時半くらいで受け付けています。
祈祷を考えている方は、検討している神社に、予約が必要か、祈祷の受付時間などを確認をしてみましょう。
七五三のお参りのいつが混雑するかおすすめの時期は?
七五三の日とされる11月15日は祝日ではなく、平日になる年もあれば、土日になる年もあります。
平日は学校や仕事の都合もあるため、11月15日周辺の土日祝が混雑する時期になります。
混雑を避けるために時期を多少ずらす人も多く、10月~12月前半がお参りの混む時期となります。
神社のご祈祷は年中受付をしている神社も多く、時期をずらす場合は、事前に確認しましょう。
また、ご家庭によっては六曜を重視する方もいるため、大安の日はより混みやすくなります。
まとめると11月15日周辺の土日祝で大安の日などが、その年の七五三の一番混む時期となります。
この時期を中心に離れるにつれ徐々に混雑が緩和されてきます。
おすすめの時期は、9月後半から10月になり、涼しくなってきた早めのタイミングです。
10月後半になると混雑が大きくなりますし、8月はまだ暑いため、9月後半から10月の涼しくなりつつも混雑する前にお参りに行くのがおすすめです。
また、余裕のある方は夏前にお参りに行くことや、寒くても大丈夫な方は12月に行くことも混雑していないという点ではおすすめになります。
七五三のお参りは六曜(大安・先勝・先負・友引・赤口・仏滅)を気にするべきか
六曜とは?六曜の由来
六曜とは日の吉兆(よいこと、おめでたいことの前触れ)を判断する考え方の一つです。
14世紀頃に中国から日本に伝えられたとされています。
幕末以降に広まり、江戸時代の終わり頃から、現在のように日の吉兆を占うものへと変化したとされています。
六曜の信憑性は?
六曜の信憑性は低いとされることが多いようです。
理由として、
・様々な歴史を経て今の時代のものに名称や順序も変わっていったということ
・根拠が不明なこと
・宗教とは一切関係がないこと
などが挙げられます。
明治時代には、暦注が流行し、信じた人が暴走してしまうことが現れました。
その結果、暦注は迷信であるとして、使用が禁止されたという歴史もあります。
六曜の日付の決まり方
いつがどの六曜になるかは
・各月の1日が六曜のうちの何になるか
・どういう順序で六曜が割り振られるか
の2点で決まります。
まず各月の1日がどの六曜になるかに関しては、
・1月、7月の1日は「先勝」
・2月、8月の1日は「友引」
・3月、9月の1日は「先負」
・4月、10月の1日は「仏滅」
・5月、11月の1日は「大安」
・6月、12月の1日は「赤口」
となっています。
1日の六曜が決まると、そこから、
先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口
の順で割り振りがされます。
六曜の意味
・大安
六曜の中でも最も吉日とされています。
「おおいに安し」を意味し、1日を通して万事において良きを維持できるとされます。
開業や開店、登記、建築、オフィス移転なども、六曜の中で大安が最もふさわしいとして選ばれやすい傾向があります。
・友引
結婚式や入籍などおめでたい行事は歓迎され、大安に続いて選ばれやすい傾向があります。
元々は共に引き分け、勝負がつかない日であるとされていました。
現在は友を引くという意味で捉えられるようになっていて、幸せのお裾分けに適した日、一方亡くなった人が友を呼び寄せる日といった意味を持ちます。
そのため、結婚式は歓迎されるが、葬式は避けるべきとされます。
時間帯としては、朝夕が吉で、11時~13時が凶とされます。
・先勝
できる限り先回りして動いた方が良いとされています。
「先んずれば勝ち」という意味をもち、午前は吉、午後は凶とされます。
予定があるならば、午前中にしておくべきとされます。
・先負
何事も控えめに平静を保つ日とされています。
また、争いごとにも向かない日とされ、訴訟や勝負事や、契約なども良い結果を得られないとされます。
「先んずれば負ける」という意味を持ち、午前は凶、午後は吉とされます。
どうしてもこの日に何かすべきことがある場合は、14時以降にできるかどうかをあらかじめ検討しましょう。
・赤口
六曜の中で、凶とされます。
赤い口の鬼に由来し、災いをもたらす日とされています。
また、赤という字のイメージから、火や刃物の取扱に注意すると言った意味合いもあります。
友引とは逆に、11時~13時にあたる時間帯は吉となります。
赤口の日に何かする予定の場合は、11時~13時にすませておくと安心です。
・仏滅
六曜の中で最も凶日とされます。
元々は「虚亡」と呼ばれ、その後「物滅」に変わり、現在の「仏滅」になったとされます。
文字通り尊い仏をも滅ぼすという意味を持ち、基本的に何をしても良い結果を得られないとされます。
ただし、最近に関しては、滅びることで新たなスタートを切れるといったポジティブな考え方をし、あえて仏滅を選ぶ場合もあります。
七五三では六曜を気にするべきか
七五三は日本の神道に由来し、六曜は中国の思想で俗信とされるため、七五三のお参りの際は、基本的には気にしなくても良いとされています。
また、六曜は宗教とも無関係で、神社は仏滅でも祈祷を受け付けています。
ただし、六曜を重視する方もいることには注意が必要です。
親族に六曜を気にする方がいるかどうかを確認し、気にする人がいる場合は、六曜を意識した七五三お参りの日を定めるとよいでしょう。
七五三のお参りは神社やお寺などどこへ行くべきか
七五三お参りに神社へ行く場合にどの神社へいくべきか
神社の分類について
七五三のお参りの神社を決める前に、まずは基礎知識として神社の分類について理解しておきましょう。
はじめに、分類の一つ目として、「氏神神社」があります。
氏神神社とは氏神様を祀る神社のことで、血縁や地縁によって決まります。
氏神様は自分の住んでいる土地を守る神様とされます。
同じ氏神様をお祀りする人達のことを「氏子」と呼び、同じ氏子が住む地域を氏子区域と呼びます。
氏神様は、元々血縁関係のある氏族同士で祀る神様とされていました。
昔は多くの人が一生涯を同じ土地で過ごしていましたが、時代と共に、土地を移住することが増え、氏神様は同じ一族の神様から、その人が住む土地の神様としての意味合いが強くなってきました。
次に「崇敬神社」があります。
崇敬神社は血縁や地縁に関係なく信仰する神社のことです。
崇敬神社を信仰する人達を崇敬者とも呼びます。
また、神様の中で別格とされる天照大御神を祀る「伊勢神宮」があります。
天照大御神は天皇の祖先とされ、伊勢神宮は日本の国土・国民を守る神社とされています。
自分の住んでいる地域の氏神様を把握する方法
自分の住んでいる地域の氏神様を知る方法としてはいくつかあげられます。
まずは両親や親族に聞いてみるというのが一番手間のかからない方法です。
それで分からない場合は、その土地に長く住んでいる知り合いに聞いてみるや、町内会の人に聞いてみるという方法もあります。
正確に把握するためには、自分の住んでいる都道府県の神社庁に問い合わせをしてみるという方法もあります。
七五三のお参り・参拝はどの神社?どこへ行くかなどの決まりはあるか?
七五三のお参りでどの神社に行くべきかに関しては、いくつかの考え方があるとされています。
まず、住んでいる土地を守る氏神様にお参りするのが一般的とする考え方です。
こちらは、自分が生まれた地域ではなく、今居住している地域の氏神様にお参りするのが一般的とされます。
次に、七五三のお参りはお子様の成長に感謝し、今後の健やかな成長をお祈りすることが目的のため、どの神社でも問題ないとされる考え方もあります。
七五三お参りをどの神社にするか決める際の良くある判断基準
七五三のお参りをどこにするかの良くある判断基準としては、まず自身の氏神様の神社に行くということがあります。
次に、家の近くの神社を選ぶということもあります。
この場合、移動時間が少なくスケジュール調整や手間が少ないという特徴があります。
次に、お宮参りで行った神社にお参りするということもあります。
子供の成長を同じ神様にずっと見守っていただけるのは安心感があります。
また、特別の思い入れや思い出のある神社を選ぶこともあります。
その他、有名な神社を選ぶということもあります。
七五三のお参りに有名な神社にお参りを行くと、その神社に行ったことが記念や思い出にもなります。
この機会に初めて行く神社を選ぶということもあります。
最後に、着物のレンタルをするフォトスタジオに近い神社を選ぶということもあります。
着物をレンタルし、当日支度をしてもらうフォトスタジオの近くの神社を選ぶことで、着物での移動が少なく、手間や子供の負担を少なくお参りをすることができます。
七五三のお参りでお寺にいくのは問題ないか
七五三のお参りは神社を選んでも、お寺を選んでもどちらでも問題ないとされています。
お祈りが神様になる場合は神社、仏様やご先祖様である場合はお寺となります。
神社へのお参りの方が、イメージが強い方も多いですが、これは日本の宗教が元々神道だったことから来ています。
七五三のお参りをお寺にする場合は、お寺の中によっては、祈祷をしていないこともあるため、お参り予定のお寺が七五三のご祈祷を受付しているは事前に確認が必要です。
七五三お参りの際の作法・作法・マナー
七五三お参りを神社で拝礼する場合の流れと作法・マナー
七五三の際に、お賽銭を入れて拝礼をする場合の流れは
・鳥居をくぐって神社に入る
・参道を通る
・手水舎で心身を清める
・社殿前で一礼し、お賽銭を入れて鈴を鳴らす
・鳥居をくぐり神社を出る
という流れになります。
鳥居をくぐって神社に入る
鳥居は一般社会である俗世と神様がいる神域を区切る結界を意味します。
神社内は神様が祀られた神聖な場所のため、鳥居の前で身なりを整え、中央を開けた場所で一礼をしてから鳥居をくぐります。
参道を通る
参道の真ん中は正中と呼ばれ、神様が通る道とされます。
そのため、参道を通る際は端を歩きます。
真ん中を横切る際は軽く頭を下げながら通ります。
手水舎で心身を清める
右手で柄杓をとって水を汲み、左手に水をかけて左手を清めます。
その後、柄杓を左手に持ち替え、右手に水をかけて右手を清めます。
両手が清められたら柄杓を右手に持ち直し、左手に水を溜めて口に含みすすぎ口を清めます。
最後に柄杓を立てるようにして柄の部分に水を流し伏せて元の場所に戻します。
これらの動作を柄杓1杯の水で対応します。
社殿前で一礼し、お賽銭を入れて鈴を鳴らす
社殿に着いたら、まずは一礼し、お賽銭をそっと入れます。
この際、お賽銭を強く投げ入れるのはマナー違反になります。
鈴があれば鳴らし、神様に自身が来たことを知らせます。
二礼二拍手一礼
姿勢を正し、深いお辞儀を2回し、右手を少し下にずらして、柏手を2回打って手を合わせ、子供の無事成長を神様に感謝し、今後の健やかな成長をお祈りします。
最後にもう一度深くお辞儀をして終えます。
鳥居をくぐり神社を出る
神社を出る際も、鳥居をくぐる前に神社の方を向き一礼をしてから、鳥居をくぐり神社を出ます。
七五三お参りの際、神社で祈祷を受ける場合の流れと作法・マナー
七五三の祈祷の流れは、まず受付から始まります。
社務所がある神社の場合は社務所で申込用紙を記入します。
その際に初穂料を納めます。
受付が終わったら、待合室にてご祈祷の順番を待ちます。
順番が来たら案内に従って社殿へと進みます。
社殿で祈祷の儀式が始まります。
まずは修祓と呼ばれるお祓いをして心身を清めます。
その後、神職が神様と参拝者の間をとりもつ祝詞を奏上します。
神職が祝詞を奏上する間は頭を下げておきます。
その後、玉串を呼ばれる榊の枝に紙垂をつけたもので神様に捧げ、拝礼します。
以上が祈祷の一般的な流れになります。
感染症対策などもあり、流れが異なる神社も多いため、気になる方は神社のHPを確認してみましょう。
七五三お参りをお寺で参拝をする場合の流れと作法・マナー
お寺で参拝をする場合の流れは、
・山門を通ってお寺に入る
・手水舎で心身を清める
・常香炉の煙で体を清める
・鐘楼で一礼して鐘を撞く
・本堂でお賽銭を入れ拝礼
・焼香台で焼香をする
・山門で一礼してお寺を出る
山門を通ってお寺に入る
山門は俗世との境を表す門とされます。
お寺の参拝前はまず身なりを整えます。
山門(入口)の前で本堂の方を向いて合掌一礼してから入ります。
敷居は踏まずにまたいで進みます。
この際、女性は右足から、男性は左足からと、入る足が異なるとされる場合もあります。
手水舎で心身を清める
手水舎で手と口を清めます。この方法は基本的に神社の手水舎での作法と同じです。
右手で柄杓を持って、左手を清め、柄杓を持ち持ちかえて右手を清めます。
最後に手のひらに水を溜めて口に含み、軽くすすいで口を清めたら、左手で口元を隠して、そっと水を吐き出します。
常香炉の煙で体を清める
常香炉があれば、煙で体を清めます。
お線香を供え、煙を受けて心身を清めます。
この際、お線香の火は口で吹き消すのではなく、手で風を送って消します。
鐘楼の作法とマナー
鐘楼を撞いてよいお寺の場合は、参拝前に仏様への挨拶の意味で撞きます。
鐘を撞く前に合掌一礼して心を整えます。
鐘を撞いた後は、合掌してお祈りし、合掌したまま一礼をします。
鐘を撞くのは基本的に本堂での参拝前に行います。
本堂でお賽銭を入れ拝礼
本堂でお賽銭を入れるときは合掌して一礼をします。
お賽銭は投げ入れるのではなく、そっと入れ、鰐口があれば鳴らします。
鰐口は参拝前の挨拶や音色をお供えする意味があります。
その後、合掌しながら一礼し、お願いごとがあれば念じます。
再度一礼して本堂を後にします。
焼香台で焼香をする
焼香台があれば、焼香をします。
合掌して礼をして、右手の親指と人差し指と中指でお香をつまみます。
左手を右手の下に添え眉間の高さまで、持ち上げます。
その後香炉の炭の上に丁寧にお香をくべ、合掌して礼をします。
焼香の回数は宗派によって異なることがありますので、不安な場合は1回にします。
山門で一礼してお寺を出る
お寺を出る際は、山門の前で再度一礼し、山門を出ます。
七五三初穂料とのし袋(熨斗袋)の事前準備と初穂料の料金相場
七五三の祈祷の際、初穂料の料金の相場としては5,000円~10,000円が一般的です。
初穂料の料金・費用は神社によって異なるため、事前に祈祷を考えている神社のHPや問い合わせをして、金額を確認しておきましょう。
初穂料とのし袋(熨斗袋)の準備は、まずはのし袋(熨斗袋)を準備します。
七五三のお参りの際は、のし袋(熨斗袋)は紅白の水引が蝶結びになっているものを用意します。
次に、のし袋(熨斗袋)に毛筆や筆ペンを使用して、記入をしていきます。
のし袋の書く場所は、
・のし袋(熨斗袋)表面
・中袋表面
・中袋裏面
・のし袋(熨斗袋)裏面
があります。
のし袋(熨斗袋)の表面には、中央上部の水引の上くらいの位置に、「初穂料」または「御初穂料」もしくは「御礼」と記載します。
中央下部にフルネームでご祈祷を受ける子供の名前を書きます。
この際の文字は上部に書いた文字よりも小さく書きます。
また、神主の読み間違えを防ぐため、名前の横にふりがなを書いておくと安心です。
中袋の表面には、中央やや上に金額を記入します。
金額は漢数字で記入します。旧字で記入するとより丁寧です。
中袋の裏面の左下に「郵便番号」、「都道府県からの住所」、「氏名」を記入します。
のし袋(熨斗袋)の裏面には、中袋がなかった場合に、左下に「金額」、「郵便番号」、「都道府県からの住所」、「氏名」を記入します。
七五三の初穂料の際のお金の包み方は、お札を表にして、印刷されている人物の顔が上に来るように入れます。
のし袋の中に入れるお札は新札を入れるようにします。
のし袋(熨斗袋)は、お祝いごとでは下の折を上の折にかぶせます。
初穂料やのし袋に関しては以下記事で詳細を解説しています。
【七五三】のし袋(熨斗袋)とは?意味・由来・書き方・マナー等を解説
七五三の祈祷後にもらえることの多い千歳飴とは
七五三でもらう千歳飴とは
千歳飴は、七五三などでの祝い菓子とされます。
原料は水あめと砂糖で、別名「せんざい飴」や「千年飴」、「寿命飴」とも呼ばれます。
千歳飴の特徴
千歳飴の特徴として、まず名前があげられます。
千歳という名前から長い年月を意味し、いつまでも健やかに長生きできるようにという想いが名前に込められています。
色は縁起の良い色とされている紅白で2本セットになっていることが一般的です。
ただし、現在はおしゃれさを重視したカラフルな色の千歳飴もあります。
形は細長い形をしていて、細く長く生きますようにという意味が込められています。
サイズは直径1.5cm、長さ1m以内と決められています。
千歳飴の袋の特徴
千歳飴の袋には縁起物として鶴亀や松竹梅が描かれていることが多いです。
鶴亀は、「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、長寿のシンボルとなっています。
また、松竹梅は、同じく長寿を示す縁起物とされています。
松は冬でも枯れず青々としていることや寿命が数百年とも言われることから長寿の象徴になっています。
竹は折れにくく成長も早いことから生命力や成長の象徴とされます。
梅は老木となっても、春もまだ遠く寒い頃から香り高い花を咲かせるため気高さや長寿を意味します。
千歳飴の意味・由来
千歳飴の意味は飴、袋ともに一貫して、子供の今後の健やかに長生きすることへの願いを込めたものとなっています。
また、千歳飴の由来は江戸時代とされています。
千歳飴の発祥は説がいくつかあります。
まず、大阪の飴売りを発祥とする説です。
大阪の飴売りが飴の販路を拡大するために、江戸に出て飴を売り始めました。
その飴を食べれば千歳まで生きられるとして、人気になったことを発祥とする説があります。
また、江戸の飴売りが紅白の飴を千年飴として売り始め、これが縁起の良い飴として評判になったという説もあります。
他にも神田明神の社頭で売られていた飴が発祥になったとされる説もあります。
七五三の際、千歳飴はどのように手に入れるのか?
七五三では定番となっている千歳飴ですが、実際はどのように手に入れるのでしょうか?
もらう場合と買う場合があります。
まずもらう場合は、神社のご祈祷を受けるともらえる場合があります。
七五三のシーズンに神社でご祈祷を受けると、千歳飴を配っている神社も多くあります。
ただし、期間限定の場合や、なくなり次第終了になる場合が多いので、事前にご祈祷を考えている神社に確認しておくと安心です。
また、親族にもらう場合もあります。
千歳飴は七五三のお祝いのお菓子とされ、親戚からの贈り物に用いられる場合も多くあります。
一方買う場合は、七五三の時期である11月が近づいてくるとスーパーやデパートに千歳飴が売られるようになります。
他にもネットショップで購入することもできます。
千歳飴の食べ方
千歳飴は縁起の良い形をしていますが、細長く食べにくい形をしています。
長生きするという意味が込められていますが、食べる際は、切ったりして食べやすいサイズにして食べても問題はありません。
神社でのご祈祷の帰り道に歩きながら食べるのは、転んだりした際に危ないので避けるようにしましょう。
七五三の千歳飴に関してはこちらの記事でも解説しています。
七五三参拝・祈祷の際の持ち物
【七五三お参り持ち物】事前に準備しておきたいお金関係の持ち物
七五三のお参りではお金が必要な場合がいくつかあります。
当日持ち合わせがなく、慌てないように事前に確認して準備をしておきましょう。
初穂料とのし袋(七五三お参りでご祈祷を受ける場合のみ)
七五三のお参りでご祈祷を受ける場合は、ご祈祷のお礼として初穂料を納めます。
初穂料の相場は、大体5,000円~10,000円になります。
初穂料の金額は神社によって定められていますので、事前に神社のHPやお問い合わせをして確認しておきましょう。
初穂料はのし袋に入れて納めます。
のし袋の準備の仕方
七五三の場合は、紅白の水引がついた、蝶結びののし袋(熨斗袋)を使用することが一般的です。
のし袋の書く場所は、
・のし袋(熨斗袋)表面
・中袋表面
・中袋裏面
・のし袋(熨斗袋)裏面
があります。
のし袋(熨斗袋)の表面には、中央上部の水引の上くらいの位置に、「初穂料」または「御初穂料」もしくは「御礼」と記載します。
中央下部にフルネームでご祈祷を受ける子供の名前を書きます。
この際の文字は上部に書いた文字よりも小さく書きます。
また、神主の読み間違えを防ぐため、名前の横にふりがなを書いておくと安心です。
中袋の表面には、中央やや上に金額を記入します。
金額は漢数字で記入します。旧字で記入するとより丁寧です。
中袋の裏面の左下に「郵便番号」、「都道府県からの住所」、「氏名」を記入します。
のし袋(熨斗袋)の裏面には、中袋がなかった場合に、左下に「金額」、「郵便番号」、「都道府県からの住所」、「氏名」を記入します。
七五三の初穂料の際のお金の包み方は、お札を表にして、印刷されている人物の顔が上に来るように入れます。
のし袋(熨斗袋)はお祝いごとでは下の折を上の折にかぶせます。
のし袋に関してこちらの記事でより詳しく解説をしています。
【七五三】のし袋(熨斗袋)とは?意味・由来・書き方・マナー等を解説
お賽銭用の小銭
お賽銭用の小銭を事前に準備しておきます。
七五三のお参りで家族で行く場合は、人数分のお賽銭の小銭を用意しておきます。
お賽銭の金額は明確な決まりがありませんが、語呂に合わせる方針では以下のような金額が、縁起が良いとされています。
・5円:ご縁がある
・15円:十分なご縁がある
・25円:二重のご縁がある
・115円:いいご縁がある
・125円:十二分なご縁がある
・415円:よいご縁がある
七五三お参りの際のお賽銭に関するより詳細の内容はこちらの記事で解説しています。
【七五三お参り】お賽銭はいくらが適切?おすすめの金額は?
駐車場の駐車料金(神社に車で行く場合)
神社の駐車場は駐車料金がかかる場合も多いので、駐車料金分のお金も忘れず用意しておきましょう。
【七五三お参り持ち物】着物を汚さないための持ち物
七五三のお参りでは着物を汚さないことも重要です。
着物を汚してしまうと購入の場合も、レンタルの場合もクリーニング料金が発生してしまいます。
着物を汚さないための持ち物を事前に確認し、準備しておきましょう。
着物で食事をする場合はタオルやエプロン・ハンカチを用意
七五三のお参り後に、食事会に行く家族も多いかと思います。
基本的には、着物を着換えてから食事会に行くのが安心です。
着物で食事をする場合は、タオルやエプロン、ハンカチを使用して、着物を汚さないようにしましょう。
タオルやハンカチは手水舎で手や口を清める際、手を拭くときにも必要です。
天気が悪い可能性がある場合は雨具(傘・レインコートなど)
お参り当日の天気が悪いと、雨水や泥で着物が汚れてしまう可能性があります。
当日の天気で雨が予想される場合は、着物を汚さないよう雨具として、傘、レインコートなどを準備しましょう。
【七五三お参り持ち物】着物や草履がしんどくなった時のための持ち物
着替えがしんどくなった場合の着替え
子供は慣れない着物で、お参り時に着物の締め付けがしんどくなる可能性があります。
また参拝後に食事を予定している場合は、先に着替えをしておくことで、食事を楽な服装でリラックスして食べることもでき、汚す心配もなくなります。
参拝後に着物を着換えられるように、着替えを持参しておきましょう。
草履が痛くなった場合に備えて靴と靴下・絆創膏
子供は慣れない草履に靴擦れや鼻緒ズレが起き、足が痛くなる可能性があります。
特に新品の草履は鼻緒も固く、より足が痛くなりやすくなっています。
足が痛くなったら早めに草履を履き替えられるように靴と靴下を準備しておきましょう。
また、靴擦れや鼻緒擦れが起きてしまった場合に備えて、絆創膏を持っておくと安心です。
【七五三お参り持ち物】その他あると便利なもの
お参りの写真撮影をするためのカメラ
フォトスタジオで写真撮影をされる方も多いと思いますが、お参り時の写真も大事な記念の一つになります。
子供や家族のお参りの様子を写真や動画で残しておけるように、カメラを用意しておきましょう。
バッテリー切れやメモリーカードの容量不足、メモリーカードの入れ忘れがあると撮影ができないため、注意しましょう。
当日スムーズに撮影が出来るように、事前に操作方法などを確認し、試し撮りもしておきましょう。
気温が低そうな場合は手持ちカイロ、ブランケット、ストールなどの防寒具
七五三の日は一般的に11月15日とされ、11月以降は肌寒くなる日も増えてきます。
天気予報を確認し、寒そうな場合は防寒具を用意しましょう。
カイロは手持ちがおすすめです。
着物は身体への締め付けもあるため、貼るカイロの場合は低温火傷の可能性があります。
その他ストールやブランケット、レギンスなども寒さを凌ぐうえで便利です。
ヘアセットが崩れた時はヘアピンがあると便利
子供が動き回る場合、移動中に寝てしまった場合は、ヘアセットが崩れることもあります。
ヘアセットが崩れた場合はヘアピンがあると便利です。
包装された一口サイズのおやつ
七五三は支度からお参りなど、子供が頑張る時間も長くなります。
子供にあげるためのおやつがあると便利です。
おやつは着物や手を汚さないよう一口サイズのもので、一つずつが包装されているものが便利です。
こぼれて着物を汚さないようにストロー付の水筒
子供の飲み物として、水筒を用意します。
水筒はこぼして着物を汚してしまうことに注意しましょう。
ストロー付のものは、飲み物をこぼしにくいので便利です。
奈良で七五三の写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ
フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。「ワタナベの七五三」にて七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルや当日支度を行っています。家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。詳細は以下リンクをご覧ください。
・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら
・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら
フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧
・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)
0742-26-3344
・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)
0742-41-1188
・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)
0742-34-5001
・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)
0744-25-6000
・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)
0745-55-0110
・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)
0774-75-1800
関連ページはこちら
同カテゴリの記事はこちら
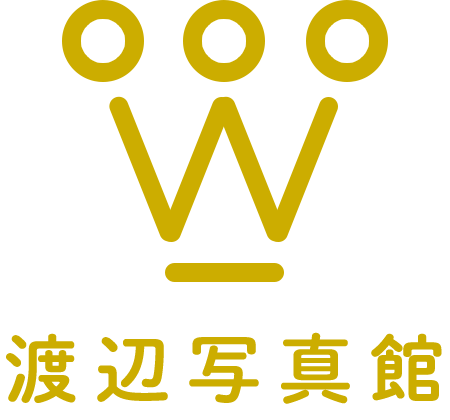

 公開日2025年1月5日
公開日2025年1月5日 更新日2025年1月24日
更新日2025年1月24日








