
お宮参りをしたいけど、どんなことをするのか?何を用意すればいいのか?そもそもお宮参りってどんなお参り? 本記事ではこれからお宮参りをするにあたって必要な知識を、伝統的な習わしから最近の傾向なども踏まえて徹底解説していきます。
目次
お宮参りとは
【お宮参りとはどんな行事?】赤ちゃんの誕生を祈願する日本の伝統行事
お宮参りとは、生後1ヶ月頃に赤ちゃんの誕生を氏神様や産土神様に報告・感謝し、健やかな成長を祈願する日本の伝統行事です。
呼び方も様々で、「初宮参り(はつみやまいり)」「初宮詣(はつみやもうで)」などありますが、現代では「お宮参り」が一般的に広く使われています。
氏神様や産土神様は、その人が産まれる前から死ぬまでを見守ってくれている神様だと信じられています。
【お宮参りとは具体的に何をするのか?】神社に参拝しご祈祷を受ける
お宮参りの当日は、まず神社やお寺で参拝し、ご祈祷をうけ、その後に挨拶まわりや写真撮影、食事会などを行うのが一般的です。
また、最近では写真館で記念撮影される方や、食事会とお食い初めを一緒に行う方も増えてきています。
お宮参りをする意味
【なぜお宮参りをするのか?】健康祈願・生活に区切り・地域の仲間入り
お宮参りをする意味については、色々な考え方があります。
<生まれた赤ちゃんの健康祈願のため>
1つ目は、生まれたばかりの赤ちゃんが元気に育つよう、自分たちを見守ってくださっている縁の深い神様にお祈りをするためという考え方です。
日本では古くから、「産土神」という生まれた地域を守っている神様や、「鎮守神」という国や地域・場所などを守っている神様、「氏神」と呼ばれる祖先など血縁的なつながりがある、または一族に深い縁のある神様が存在するとされています。
現代ではこれらの神様は明確に区切られているわけではなく、産土神様や鎮守神様をひっくるめて氏神様と呼んでいる場合もありますが、どの神様も自分たちの守り神様であるといえます。
そのような神様に、赤ちゃんが無事に生まれたことを感謝し、今後の健康を祈願していたそうです。
これには、昔は現代よりも医療が発達していなかったため、赤ちゃんの生存率が低くかったこと、子供たちが健康に育つのは難しいことだったことが関係しています。
生まれたばかりの赤ちゃんが健やかに成長してほしいという願いは、今も昔も変わらないようです。
<生活に区切りをつけるため>
2つ目は、これまでの日常と、これからの日常に区切りをつけるためという考え方です。
お腹の中で赤ちゃんを守っていたお母さんが、出産を経ていつもの生活に戻ってきた、という一区切りとしての役割があるとされています。
また、赤ちゃんが生まれたということは、家族の一員が新しく増えたということにもなります。家族みんなが新しいスタートを切るという意味においても、お宮参りはちょうど良い区切りの行事といえますね。
<地域の仲間入りをするため>
3つ目は、赤ちゃんが地域の仲間入りをするために、皆さんへ向けて挨拶をするためという考え方です。
1つ目の考え方でも触れましたが、日本には自分たちの守り神様がいるとされています。その守り神様に地域の一員として認めてもらうためにご挨拶するというものです。
これは「氏子入り」とも呼ばれています。
「氏子」とは氏神様を信仰している人たちのことです。
赤ちゃんが生まれたとき、氏子の仲間入りをすることで地域の人たちにも認めてもらう、つまり社会的な認知を得るための儀式だったとされています。
以上の3つが、お宮参りをする意味とされています。
伝統的な行事ですので、時代背景が少し昔の話もございます。上記のお宮参りをする意味が、かならずしも現代に当てはまるとは言えませんが、ぜひお宮参りの参考にしてください。
【お宮参りの風習】額に文字、悪霊よけのおまじない
お宮参りでは、神様に赤ちゃんの泣き声を聞いてもらったり、赤ちゃんの額に墨をつけたりする風習があります。 額の墨に関しては、赤色で大の文字が書かれているのを目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
<なぜ額に文字を書くの?>
お宮参りの際、赤ちゃんの額に文字を書くのは「綾子(あやつこ)」という関西特有の風習です。
平安時代の宮中が発祥とされていて、額に「×」「大」「小」「犬」を書くことで悪霊よけのおまじないをおこなっていたそうです。
また、宮中では紅を用い、一般庶民は鍋の墨を用いていたとされています。
お宮参りの由来
お宮参りの呼び方
お宮参りには時代や地域によって様々な呼び方があります。
昔は「日の晴れ(ひのはれ)」「日明け(ひあけ)」「忌明け(ゆみあけ)」「産明け(うぶあけ)」「見参参り(げんぞまいり)」「氏見せ(うじみせ)」「産土詣(うぶすなもうで)」など多くの呼び方があったとされています。現在では、「お宮参り」「初宮参り」「初宮詣」と呼ばれることが多いです。
「日の晴れ」「日明け」「忌明け」「産明け」 ・・・その由来は?
古くは、死やあの世、またはそれらを連想させる血といったものが「穢れ(けがれ)」であると認識されていました。
この穢れは「気枯れ」と書かれることもあるのですが、これは気の乱れや、心身の不調、生命力が弱っているというような状態を表しています。
<産の忌みとは?>
お産には出血を伴うことから、お母さんや赤ちゃんには穢れが残っていると考えられてきました。
お母さんや赤ちゃんは、この「産の忌み(さんのいみ)」と呼ばれる穢れがなくなるまで、産小屋に入って他の人たちと接触しないよう隔離されていたとされています。
この期間が終わることを忌が明けるとも言うのですが、これは穢れがなくなったという意味です。
赤ちゃんの忌が明けるのがおよそ30日とされており、これが上記の名前の由来です。
ちなみに、お母さんの忌が明けるのはもう少し時間が経ってからと考えられていたようで、産後75日とされていました。
お宮参りはお母さんの「産の忌み」の期間中に行うことになりますので、赤ちゃんとお参りに行くのはお父さん、父方のおじいちゃん、おばあちゃんでした。
特に、赤ちゃんを抱っこしていたのはおばあちゃんだったようです。
このように、昔の呼び方から色々な事が分かります。
しかし、現在において「穢れ」の風習は重要視されていませんので、お母さんも気にすることなくお宮参りを楽しんでください。
【お宮参りの歴史】起源から一般化まで
現在では一般的になっているお宮参りですが、いつ頃から始まったのか皆さんはご存知でしょうか?
<お宮参りの起源>
大昔から、赤ちゃんが生まれたことを祝い、健康を祈願する行事自体は存在していました。
やはり、医療が発達していなかったことから、赤ちゃんが元気に成長するには厳しい時代でしたので、こういった行事が催されていました。
行事の内容は主に、ご馳走を食べたり、神様にお祈りしたりすることだったようです。
この行事がお宮参りの起源とされています。
<お宮参りの一般化>
そして鎌倉時代になると、今度はお宮参りの元となる風習が始まり、室町時代で現在のようなご祈祷を受ける儀式に変化して行きました。
先駆けは、室町幕府三代将軍・足利義満が誕生した際のお参りとされており、そこから人々に広まって一般的な儀式へとなっていきました。
お宮参りにはいつ行くの?
【お宮参りをするタイミングは?】男の子は生後31日目、女の子は生後33日目、しかし
地域による違いはありますが、お宮参りでは生まれた日を1日目として数え、そこから生後1ヶ月頃に行くのが習わしです。
また、
伝統的には「男の子は生後31日目、女の子は生後33日目」に行うとされています。
現代では、1ヵ月検診を目途にお宮参りの日程を組むことも多いです。
しかし、これらの日数はあくまで目安程度に考えておいて大丈夫です。
お宮参りの日付を決めるポイント
<家族の都合を考慮する>
お宮参りは赤ちゃんの初めてのお祝い事なので、家族の皆さんが集まれる都合の良い日を選ぶことも大切です。
<実は大安にこだわらなくても大丈夫>
大安、先勝などの六曜は「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」という思想をもとにした中国発祥の占いです。
そのため、六曜は日本の宗教や神社とは直接的な関係がありません。しかし、親族の中に六曜を気にする方がいる場合は、事前に相談しておくことをおすすめします。
【お宮参りの時期をずらしてもいい?】体調最優先、生後6ヶ月頃まで大丈夫!
お宮参りの時期は、生後1ヶ月頃という伝統にこだわらなくても全く問題ありません。それよりも、生まれたばかりの赤ちゃんや、産後間もないお母さんの体調を万全に整えることを最優先しましょう。
特に、時期によっては生後 1か月に外出することはかなりのリスクを伴います。
真夏であれば熱中症、真冬であれば風邪を引いてしまうかもしれません。
少し過ごしやすい季節になるまで待った方が、母子ともに安全にお宮参りに行くことができるでしょう。
一緒に行かれるご家族の予定と相談しながら、ぜひ自由に日程を決めてくださいね。
<とはいえ、いつまでずらせる?>
目安としては生後6ヶ月頃までがお宮参りを行っても良いとされている時期です。
このあたりの時期であれば、赤ちゃんとお母さんが生活に慣れて外出がしやすくなるため、ゆとりのある時期を狙って日程を調整することもできます。
お宮参りとお食い初めを同日に行うこともある!?
赤ちゃんが生後1歳になるまでに迎える主な行事には、お七夜(生後7日目)、お宮参り(生後1ヶ月頃)、お食い初め(生後100日)、ハーフバースデー(生後6ヶ月)、初節句(3月3日または5月5日)、初誕生日(1歳)があります。
行事の順序を気にするならば、お宮参りの次のイベントはお食い初めの百日祝いです。
ただ、この2つの行事は生後100日頃までに行えば大幅なずれがないので、同時期にお宮参りとお食い初めを行うこともあります。
<お食い初めとは?>
お食い初め(おくいぞめ)とは、生後100日頃に「一生食べ物に困らないように」という願いを込めて赤ちゃんに食事の真似事をさせる伝統的なお祝いの儀式です。
生後100日〜120日頃におこなうため、「百日祝い(ももかいわい)」ともいいます。
最近では、生後3カ月頃にお宮参りとお食い初めを合わせて行うことも、1つの選択肢となっています。
<お宮参りとお食い初めを合わせて行う場合の食事会>
食事会の場所は、自宅でもレストランでもどちらでも構いません。自宅であればゆっくりと過ごすことができますし、レストランであれば準備や片付けなどの手間が省けます。状況に合わせて選びましょう。
レストランで食事会をする場合は、必ずお店を予約しておきましょう。その際、落ち着いた雰囲気の個室を選ぶと安心です。
食事の内容は、家族の好みや予算に応じて自由ですが、赤ちゃんの健康や幸せを祈るために縁起物の食材が使われた「祝い膳」をいただくとよりお祝いの雰囲気が盛り上がります。
手作りであればできる範囲で、またレストランの場合は祝い膳の提供があるかどうか確認するとよいでしょう。
<一緒に行うメリット>
・日程調整がしやすい
参加者の都合を合わせやすく、特に遠方から親戚が来る場合に便利です。
・経済的負担が軽減する
衣装代や食事代などが1回分で済むため、費用を抑えられます。
・体への負担が少ない
生後1ヶ月前後のお宮参りの時期よりも、お食い初めの時期の方が赤ちゃんや母親の体調が安定していることが多く、余裕をもって行えます。
<一緒に行うデメリット>
・記念日が一度にまとまってしまう
お宮参り(生後1ヶ月頃)とお食い初め(生後100日頃)は本来それぞれ時期が異なる行事です。したがって、一緒に行ってしまうと節目ごとに成長を喜ぶ機会が減ってしまいます。
また「成長の記録」が一度にまとまってしまうため、後で振り返った時に1つ1つの思い出が薄れてしまう可能性があります。
いつお宮参りに行くかを考えるポイント まとめ
・赤ちゃんとお母さんの体調を優先する
・参加者の都合も考慮する
・大安にこだわらなくてもよい
・お参り時期をずらして穏やかな気候の時期を選ぶ
・お宮参りとお食い初めを一緒にするのも良い
お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長と幸せを祈る儀式です。体調が悪化しては元も子もなくなってしまいますので、体調最優先で日程を調整しましょう。
お宮参りする場所は?
1.赤ちゃんが生まれた土地の守り神様がまつられている神社
2.これから赤ちゃんが育っていく土地の守り神様がいる自宅近所の神社
3.有名な神社や思い入れのある神社
など
昔は、自身の住む地域の氏神様を祀る神社にお宮参りに行くものとされていましたが、現在ではこれに限りません。
有名な神社、大きな神社、家からのアクセスのよい神社、ゆかりのある神社、安産祈願にいった神社など、参拝する神社を自由に選んでも大丈夫です。
参拝する神社が決まれば、ご祈祷の予約が必要か確認しましょう
大きな神社では予約不要であることが多いですが、小さい神社などでは予約が必要である場合もあります。各神社のウェブサイトを確認するか、電話で問い合わせをしてみましょう。
また、ご祈祷の時間が決まっていることもありますので、当日のスケジュールを立てるためにも事前に確認しておきましょう。
お宮参りでの当日の流れ
お宮参り当日は、「準備 → 神社への参拝・ご祈祷 → 記念撮影 →食事会」という流れが一般的です。
赤ちゃんにとってはまだ外出に慣れない時期でもあるため、無理のないスケジュールを心がけることが大切です。
1.出発前の準備
当日の朝はまず赤ちゃんの体調を確認し、授乳やおむつ替えを済ませます。
衣装はベビードレスなどもありますが、正式な服装は祝着(のしめ)を羽織る和装です。
祝着(のしめ)とは、お宮参りの際に赤ちゃんが身に着ける伝統的な着物のことで、「一つ身」「産着(うぶぎ)」「掛け着」と呼ぶこともあります。いずれの衣装も赤ちゃんの負担にならないように、直前に着せるのが望ましいでしょう。
2.神社への参拝
多くの神社では事前予約のうえ、受付で初穂料を納めます。その際に、赤ちゃんの名前や生年月日などを記入することが一般的です。ご祈祷が始まると、祝詞の奏上や鈴での清めが行われ、赤ちゃんの健やかな成長を祈願していただくことができます。
3.記念撮影
ご祈祷を終えた後は、境内で記念撮影を行うことが多いです。鳥居や拝殿を背景に撮影すると、雰囲気が一層引き立ちます。写真館や出張カメラマンに依頼するご家庭もあれば、家族が気軽に撮影する場合もあります。
4.食事会
参拝後は、親族で食事会を設けることがあります。料亭やレストランを利用するケースが多いですが、自宅でゆっくりと祝う家庭も少なくありません。形式にとらわれる必要はなく、赤ちゃんと家族の負担にならない形で行うのが良いでしょう。現代ではお食い初めを一緒に行う場合も多いです。
近所のフォトスタジオで撮影・レンタルする場合
神社の近くには、よく写真館・フォトスタジオがあります。
近年のフォトスタジオではお宮参り衣装のレンタルも行っているため、スタジオで記念撮影を先に行い、そのまま撮影で使った衣装のレンタルをしてお参りに行くことも出来ます。
この方法なら、お金も時間も手間も省けるためおすすめです。
その場合は「準備 → 記念撮影 →神社への参拝・ご祈祷 → 食事会」といった流れになります。
お宮参りでの当日の服装を考えましょう
最も大切なことは、主役である赤ちゃんを中心に、家族でまとまりのある服装を選ぶことです。ここでいう、「まとまりがある」というのは、主役の赤ちゃんが最も格の高いものを着て、両親は赤ちゃんを引き立たせるような色合いを選ぶということです。
お宮参りの服装の注意点
・赤ちゃん:祝着(のしめ)やベビードレスの下には、動きやすく着脱が簡単な肌着を。暑さ寒さに応じて重ね着を調整できるようにすると安心です。
・母親:フォーマルなワンピースや着物が一般的ですが、授乳のしやすさを考慮することも大切です。
・父親:スーツまたはジャケットスタイルが多く見られます。
・祖父母:和装・洋装いずれも可。全体として統一感が出るよう、あらかじめ家族で相談しておくと良いでしょう。
夏・冬に持って行くと便利な物
赤ちゃんの体温調節はどうすればいい?
生まれたばかりの赤ちゃんは、自分で上手に体温を調整することができません。これは、体温調整中枢という自律神経の働きが大人と比べてしっかりと備わっていないためです。
そのため、赤ちゃんの体温は気温によって変化しやすく、周りが暑ければ体温は上がり、寒ければ下がるようになっています。
生まれてから8ヶ月程経つと、赤ちゃんは徐々に自分で体温調節ができるようになっていきますが、お宮参りの時期は一般的に生後1ヶ月ですので、お参りの時期は赤ちゃんの体温調節にも気を配る必要があります。
暑い夏、寒い冬のお宮参り・・・あると便利な物は?
お宮参りとなると、おでかけになりますのでどうしても外で過ごす時間が長くなりますよね。
赤ちゃんが快適に過ごすには、その日の天気や気温はとても重要です。特に、夏や冬は気温が高すぎたり低すぎたりと、赤ちゃんにとっても過酷な季節となります。
それでは夏や冬のお参りでは、それぞれどのようなものがあると便利なのでしょうか?
夏のお宮参りにおすすめの持ち物
日差しを遮る日傘や、保冷剤といった冷たいものなどの暑さ対策をしましょう。
・日傘
・帽子
・赤ちゃん用の日焼け止め(低刺激、無添加など)
・冷却ジェルシート
・保冷剤
・冷感タオル
・ネッククーラー
・ハンディファン
・扇子
・パパママ用の汗拭きシート
・タオル
・水筒
・保冷ボトルや凍らせたペットボトル
この他にも、木がたくさん生えている神社の場合は虫がたくさんいますので、虫除けスプレーを持っていくことをおすすめします。
赤ちゃんに虫除けスプレーをつけても大丈夫なの?
生まれたばかりの赤ちゃんに使用するなら、「イカリジン」という成分が入っているもの、またはハーブが使われているものを選びましょう。
特にこの「イカリジン」ですが、こちらは比較的最近に開発されたもので、今のところ子供への健康被害が報告されていないことから安全な成分とされています。
蚊成虫・ブヨ・アブ・マダニ・イエダニなどに効果があり、年齢制限や使用回数の制限がないのでおすすめです。
虫除け剤はスプレーのように肌に直接つけるタイプや、服などに貼り付けて使用できるシールタイプのものなどがあります。
使用の際は、説明書をよく確認して安全に害虫対策をしましょう。
「ディート」という成分には注意‼
市販の虫除けスプレーには、「ディート」という成分が含まれていることが多いです。
こちらの成分は、「イカリジン」よりも虫除けの効果は強いですが、生後6ヶ月未満の赤ちゃんには使用できませんので注意してください。
冬のお宮参りにおすすめの持ち物
ポンチョやおくるみなど、冷たい風や寒さを防げるものを準備しましょう。
・ベビーケープや赤ちゃん用のポンチョ
・ブランケット
・冬用のおくるみ
・帽子
・上着
・靴下やレッグウォーマー
・手袋
・耳当て
・マフラーや襟巻
・靴用の中敷きカイロ
・カイロ
・ヒートテックなどのインナー
・保温ボトル
・温かい飲み物
当日は赤ちゃんだけでなく、パパママやご家族皆さんの暑さ対策・寒さ対策を忘れないようにしていきましょう。
必要なものなど・準備物
お宮参りに持参しておくと安心な持ち物
・初穂料(事前にのし袋に入れて準備)
・母子手帳
・保険証(万が一の体調変化に備えて)
・おむつ
・おしり拭き
・おむつ替えシート
・ビニール袋(汚物入れとして使用)
・授乳セット(ミルク・哺乳瓶・お湯、授乳ケープなど)
・タオルやガーゼハンカチ
・着替え(赤ちゃん用、必要に応じて大人用も、祝着(のしめ)やベビードレス)
・お宮参りの小物(お守り袋、扇子、でんでん太鼓、犬張子、紐銭)
・ベビーカーまたは抱っこ紐
・記念撮影用のカメラやスマートフォン
【お宮参りの小物】縁起物とされる習わし
お宮参りには、昔から縁起が良いとされる小物を身に着け、お寺や神社へ参拝する習わしがあります。
お宮参りの小物は地域によって異なりますが、赤ちゃんを抱っこしたとき、祝着(のしめ)の紐を通じて抱っこする人の背中にぶら下がるように結び付けるのが一般的です。
<小物のつけ方>
赤ちゃんを抱いた上から抱いた人の体ごと覆うように掛け、抱いている人の背中で紐を結びます。
扇子に付いている麻の紐を伸ばし、でんでん太鼓、犬張子、お守り袋の順番で小物同士を結び付けます。 紐銭は紅白あるいは金銀の水引で結び付けます。
落ちてくることのないよう、麻の紐を産着の紐にしっかりと結び付けましょう。
<小物の種類>
・お守り袋
お守り袋は、お寺や神社でいただいたお守りを入れる袋です。 縁起の良い「鶴」が刺繍されているものが多く、赤ちゃんの長寿の願いが込められています。
・扇子
扇子はその形から「末広(すえひろ)」とも呼ばれ、赤ちゃんのこれから先の人生が末広がりであるように、という願いが込められています。 お宮参りの扇子はのし袋に入れられ、麻の紐が添えてあります。 麻の紐には「麻のように丈夫に育つ」という意味があります
・でんでん太鼓
赤ちゃんのおもちゃとして親しまれているでんでん太鼓も、お宮参りに用いられる小物の一つです。 すべて丸い面で表も裏も同じ形のでんでん太鼓には「おだやかで裏表のない子に育ちますように」という願いが込められています。また「太鼓の音は魔物を祓う」ともいわれており、魔除けとしての役割もあります。
・犬張子
犬張子は紙でできた犬の形の置物です。 犬の子どもは大きな病気もせずにすくすくと成長することから、「健康で丈夫に育つように」という願いが込められています。狛犬が原型とされている犬張子には魔除けや厄除けの意味もあり、子どもが数え年で3歳になるまでの災難を犬張子は身代わりになって引き受けてくれるといわれています。 お宮参り後は丁寧に保管し、3歳の七五三の際に奉納しましょう。
・紐銭
紐銭とはいただいたお祝儀を麻の紐に通したもののこと。「将来お金に困らないように」という願いが込められており、主に関西を中心に見られる風習です。
<小物は必要?>
「必ず付けないといけない」ということはなく、何も付けずに参拝しても問題ありません。
<小物はどうやって用意する?>
お宮参りの小物の入手方法は購入かレンタルです。
購入する場合、デパートや着物店などであれば実際に手に取って選ぶことができます。
インターネット通販も手に入りやすいのでおすすめです。
実店舗でもネットでも必要なものが一式セットになったものが用意されています。
しかしセットによって内容が異なったり、男の子と女の子で分けられていたりするため、購入時はしっかり確認するようにしましょう。
レンタルする場合、より費用を抑えることができます。
フォトスタジオなどで記念撮影をすると、衣装と一緒に小物をお得にレンタルできる場合があります。
レンタルならお参りの後に返却するだけなので、その後のお手入れや神社への奉納までの保管方法などに悩まされることがないのも魅力的です。
お宮参り「初穂料」、「祈祷料」の金額相場
神社にて祈祷を受ける際には「初穂料(はつほりょう)」「祈祷料(きとうりょう)」と呼ばれる神社への謝礼金を支払うのがマナーです。事前に祈祷の初穂料がいくらかを確認しましょう。初穂料の相場は、大体5,000円~10,000円です。初穂料の金額は神社によって定められていますので、事前に神社のHPチェックやお問い合わせをして確認しておきましょう。初穂料はのし袋に入れて納めます。
「封筒」ではなく「のし袋(熨斗袋)」を準備
お宮参りの初穂料は、受付でお財布から直接出すのではなく、のし袋に入れてお渡しするのが丁寧な方法です。
のし袋は、普通の封筒とは異なり、「上包み(上袋)」「のし(熨斗)」「水引」「中袋」で構成されています。
のし袋に関してはこちらの記事でより詳しく解説をしていますので、ぜひご覧ください。
※七五三での利用を想定した記事内容ですが、準備方法は同じです。神社に納めるため表書きも同じく「御初穂料」で問題ありません。
【七五三】のし袋(熨斗袋)とは?意味・由来・書き方・マナー等を解説
まとめ
・いつお宮参りするか、伝統的には「男の子は生後31日目、女の子は生後33日目」に行うが、必ずこの日に行わなければならないというわけではなく、あくまで目安。生後 1か月程度~6ヶ月程度を目安に参拝すればよいでしょう。赤ちゃんの誕生を祝うという本来の目的を忘れず、柔軟に日程を決めることをおすすめします。
・お宮参りする場所は、伝統的には住む地域の「氏神様を祀る神社にお宮参りに行くもの」とされていました。しかし、現代では参拝する神社を自由に選んでも大丈夫です。
・お宮参り当日の流れは「準備 → 神社への参拝・ご祈祷 → 記念撮影 →食事会」という流れが一般的です。ですが、着物レンタルやスタジオ撮影など利用する場合は「準備 → レンタル・記念撮影 →神社への参拝・ご祈祷 → 食事会」といった流れもおすすめです。
・服装は主役である赤ちゃんを中心に、家族でまとまりのある服装を選ぶ。しかし、母子ともに無理のない範囲で季節や体調に合わせた服装でも問題ありません。
・準備物は赤ちゃんとお母さんの体調管理が出来る備えを最優先に考え用意する。参拝・ご祈祷の予約が必要か確認し、初穂料の金額なども確認する。撮影や飲食店の予約も忘れずに行いましょう。
以上の記事内容を踏まえて、素敵な思い出に残るお宮参りにしましょう!!
奈良でお宮参りの写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。お参りの撮影・着物レンタルや当日支度を行っています。家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。 詳細は以下をご覧ください。
▼奈良の神社でのお宮参りレポートはこちら
・春日大社(奈良県奈良市)のお宮参り(初宮詣)・ご祈祷レポート
・橿原神宮(奈良県橿原市)のお宮参り|ご祈祷・お参りレポート
▼スタジオでのお宮参り写真撮影に関するご案内はこちら
・お宮参り写真(初参り)|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら
▼お宮参り着物・産着レンタルに関するご案内はこちら
・お宮参り着物・産着レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら
▼春日大社など奈良のお宮参り出張写真撮影に関するご案内はこちら
フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧
・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26) 0742-26-3344
・押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1) 0742-41-1188
・柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5) 0742-34-5001
・橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1) 0744-25-6000
・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26) 0745-55-0110
・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F) 0774-75-1800
関連ページはこちら

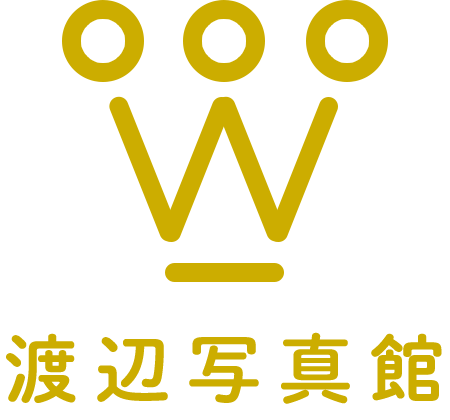

 公開日2025年9月21日
公開日2025年9月21日 更新日2026年1月24日
更新日2026年1月24日









